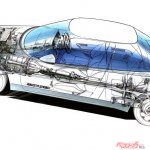巨大なマーケットを形成し、常に先端のテクノロジーが投入される自動車産業では、ユーザーの注目を集める革新的な技術がたびたび登場する。そのなかには、今後のクルマ業界を変えるとまで言われて脚光を浴びながらも、しばらくたつと話題にならなくなった技術もある。それらの技術は一過性のものだったのか? それとも別の理由で語られなくなったのか? 今回は一世を風靡した技術を紹介し、その後の推移を見ていくことにしよう。
文/長谷川 敦、写真/日産、スバル、ホンダ、三菱、マツダ、トヨタ、FavCars.com
【画像ギャラリー】技術大国ニッポンが誇る、世界をあっと言わせた自動車技術の今昔を見る(13枚)画像ギャラリー
回頭性と安定性を両立した夢の4輪操舵システム「日産 HICAS」
一般的な4輪車では、進行方向を変えたい時に車体に対する前輪の角度を変化させる。これを操舵と呼び、操舵の際も後輪の向きは一定に保たれる。
詳細な説明は省略するが、前輪の向きを変えることでタイヤと路面の摩擦によってコーナリングフォースと呼ばれる力が発生する。これでクルマは旋回できるのだが、このとき操舵されている前輪と、まっすぐ行きたい後輪でコーナリングフォースの発生に時間差が生じるとクルマの動きは不安定になる。
そこで前輪の操舵に応じて後輪も操舵してやれば、クルマはより効率良く旋回できることになる。これがいわゆる4輪操舵、または4WS(4 Wheels Steering)だ。
日産が1985年に発売したR31型スカイラインにはこの4WSが搭載されることになり、そのシステムはHICAS(ハイキャス・High Capacity Actively Controlled Suspension)と命名された。
HICASの画期的だった点は後輪の操舵に電子制御を用いたことで、単なる機械式の4WSに比べて速度に応じた繊細な制御が可能になり、操縦安定性は大きくアップした。
HICASはその後もHICAS-II、SUPER HICAS、電動SUPER HICASと進化し、R33型スカイラインGT-Rにも搭載されたが、2000年代に入るとHICASを装備する車種も少なくなる。これは車体&サスペンション設計やブレーキなどの進化により、複雑で高価になりがちな電子制御に頼らなくても操縦安定性が得られるようになったため。
とはいえ操縦安定性を高める、あるいはキビキビ曲がるクルマに仕上げる手段として4WSが有効なのもまた事実。その証拠に、近年になって4WSを装備するクルマは増えてきている。
メルセデス AMG GT S/Cやルノー メガーヌなど、設計&製造技術や素材の進歩によって、HICASでは不可能だった高度な4WS制御を実現したクルマも次々とデビューしている。そうした流れから、最新テクノロジーで武装された新世代のHICASが登場する日も近いのかもしれない。
車高調整も思いのまま! しかしメジャーにはなれず……「スバル 電子制御エアサス」
一般的なクルマのサスペンションは、路面からのショック吸収や走行中の姿勢制御に金属製スプリングを使用する。だが、一部のクルマでは金属製スプリングの代わりに空気圧を利用するものもある。これがエアサスペンション(エアサス)だ。
金属製スプリングの難点のひとつに、車重によって縮み量が変化してしまうということがある。つまり乗車人数が多かったり、荷物が重すぎたりすると、それによって車高が一気に下がってしまい、乗り心地などに影響が出る。
これを解決してくれるのがエアサスだ。空気圧によって車高を保つエアサスでは、荷重が加わったときに圧力を高めることにより、理想的な車高をキープできる。そしてそれを電子的に制御すれば、走行中の荷重変化に対してもアクティブな対応が可能になり、本来はオイル入りのショックアブソーバーが担当する減衰も空気の力で行える。
このようにメリットの多い電子制御式のエアサスペンションを日本で最初に採用したのが1984年登場のスバル レオーネだった。そしてその後を追うように国内他メーカーからも電子制御エアサスを装備したモデルが登場した。
自動車サスペンションの未来を担う技術として一時はもてはやされた電子制御エアサスだが、機構が複雑なためコスト高を招き、頻繁なメンテナンスも要求された。こうした理由から徐々に衰退してしまい、スバルも2000年代には採用をやめることになる。
車高調整が容易な電子制御エアサスは、現在でも高級車やバスなどで使用されている。コストなどの問題が解消されれば、再び注目されてもよい技術と言える。
厳格な規定をクリアした奇跡の低公害エンジン「ホンダ CVCCエンジン」
1970年のアメリカで大幅に改正された大気浄化法は、その法律改正を推奨した上院議員の名をとってマスキー法と呼ばれている。炭化水素(HC)、一酸化炭素(CO)、そして窒素酸化物(NOx)の排出を大幅に規制するこの改正法をクリアするのは、当時の市販車にとって不可能とも思われた。
さすがにこれは厳しすぎるということで、実施時期の延長などで規制は緩められることになるが、なんと1972年にマスキー法をクリアしてしまうエンジンが日本で誕生する。
ホンダが開発したCVCC(Compound Vortex Controlled Combustion)エンジンは、通常の燃焼室の他に副燃焼室を持ち、それぞれ濃度の異なる混合気を燃焼させることによって燃料効率を高めて排気ガスをクリーンにする。さらにCVCCでは排気ガスを浄化するための触媒も不要なため、コスト面でも大きなメリットがあった。
マスキー法をクリアできるエンジンの登場に世界の自動車業界は騒然となった、その影響は、トヨタもホンダの技術協力をあおいで自社の低公害エンジンを開発するほど。
CVCCエンジンは多くのホンダ車に採用されたが、電子式燃料噴射装置や触媒の進化によって通常タイプのエンジンでも排気ガスを浄化できるようになり、1980年代末にはその役目を終えている。
直噴技術の導入はいささか早計だった? 「三菱 GDIエンジン」
「直噴」もしくは「GDI」という言葉を耳にした人は多いはず。これらは同じ意味で、GDIとは「Gasoline Direct Injection engine(ガソリン直噴エンジン)」のことで、従来型エンジンでは吸気ポートに噴射していたガソリンを直接シリンダーに噴射するもの。
三菱が1996年に発売したギャランとレグナムにはこのGDIエンジンが採用され、メーカーでも量産型乗用車では世界初装備になるDGIを全面に押し出したキャンペーンを実施。全車GDI化を目指して積極的な開発を進めていた。
実際に三菱GDIエンジンに対する市場の関心は大きく、ギャラン&レグナムは1996年の日本カー・オブ・ザ・イヤーを受賞している。
だが、実際のGDIエンジンは期待されたほどには燃費性能が高くはなく、「環境にも優しい」と喧伝されたにも関わらず、NOx法にも対応できないなどのマイナス面が次第に目立つようになった。こうした理由から、2007年にはGDIエンジンの生産が終了している。
ガソリン直噴エンジン自体は可能性のある技術であり、近年のクルマでも採用例が多い。三菱GDIエンジンは、市場に投入されるタイミングが早すぎたということだろうか?
燃費アップの決定版となるか? 「マツダ 超希薄燃焼エンジン」
ガソリンエンジンでは、燃料となるガソリンを空気と混ぜて燃焼室で爆発させる。このガソリンと空気の割合を空燃比と呼んでいるが、なるべくガソリンの割合を薄くして、なおかつ高い燃焼エネルギーを得られれば、ガソリン消費量を大きく減らすことができる。
これまでガソリン1に対して空気を14.7にするのが理想的な空燃比と言われてきたが、マツダが開発したSKYACTIV(スカイアクティブ)-Xエンジンは空燃比30という希薄燃焼(リーンバーン)を実現したことで話題となった。
当然ながら、希薄燃焼の実現には大きなハードルがあった。なかでも通常の空燃比よりも窒素酸化物(NOx)の排出量が多くなるのは深刻で、環境問題を考えるとこれを避けて通ることはできなかった。
マツダはこうした問題を解決するために独自の火花点火制御圧縮着火方式(SPCCI)を開発し、30:1の超希薄燃焼と低公害性を両立してみせた。
スカイアクティブ‐Xエンジン搭載のモデルがデビューしたのが2019年。メーカーによると、これが超希薄燃焼エンジンの最終形ではなく、まだまだ改善の余地はあるとのこと。超リーンバーンエンジンの進化はこれからも続いていきそうだ。
安全性向上は永遠のテーマ「トヨタ 衝突安全ボディGOA」
事故の際に、衝撃を巧みに分散させつつ、変形によって搭乗者にダメージを与えない――これがクルマのボディの理想と言えるが、そんな理想に一歩でも近づくことを目的に開発されたのが、トヨタの衝突安全ボディのGOA(ゴア・Global Outstanding Assessment)だ。
GOAを採用したクルマの第一号は1995年12月発表の5代目スターレット。衝突時のエネルギーを効果的に分散するアンダーボディ骨格に強固なキャビンを組み合わせることで搭乗者保護性能を高めたGOAは、TV CMの「GOAください」というフレーズでも話題になった。
GOAの登場を機に、他メーカーでも自社製自動車の衝突安全性能をより強化する流れができ、それがクルマの安全性向上にも貢献している。
現在でもトヨタのクルマにはGOAの考えが継承され、もはやあって当然の基準にすらなっている。もちろん、クルマの安全性向上はこれからも変わらぬ永遠の開発目標であるのは間違いない。
爽快感と安全性の妥協点? 「Tバールーフ」
オープンカーの弱点は、屋根がないことによる剛性の低下をボディ(フレーム)側で補わなくてはならないことで、その補強のために重量増加を招いてしまう。そこで考え出されたのが、前後のウィンドウをバーでつなぐ通称「Tバールーフ」だ。
Tバールーフの発祥は1970年代のアメリカと言われており、これは当時引き上げられたクルマの安全基準に準拠させるのが目的だった。そしてその流れは日本にも波及し、一時は国内でもちょっとしたTバールーフの流行があった。
Tバールーフを採用した国産車は日産のフェアレディZやNXクーペ、そしてトヨタのMR2など。いずれもスポーツ志向の強いクルマだが、これは顧客の年齢層などを考えれば納得。
しかし、Tバールーフのクルマにはそこまでの利点はなく、実際に乗っていた経験がある人も「不便さが先に立って、ほとんどルーフを開放することはなかった」と語っている。残念ながらTバールーフは一過性の流行に終わり、近年のクルマで採用例を見ることはほとんどない。
【画像ギャラリー】技術大国ニッポンが誇る、世界をあっと言わせた自動車技術の今昔を見る(13枚)画像ギャラリー
投稿 HICAS、CVCC、GDIエンジン……一世を風靡した”ハイテク”技術はどこいった? は 自動車情報誌「ベストカー」 に最初に表示されました。