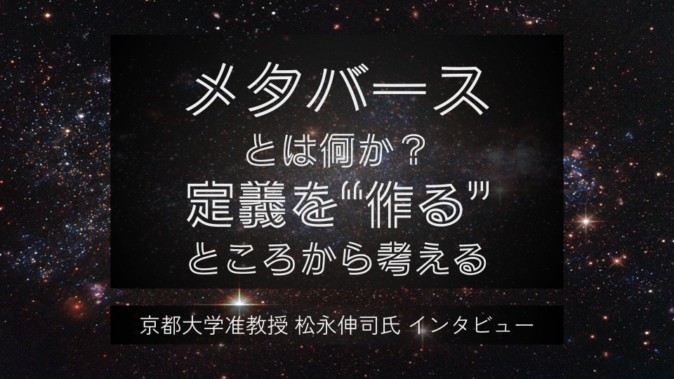「メタバース」の代表例として2000年代に世界的な注目を集めた「Second Life」。現状のブームに十数年さきがけている「メタバース社会」の先輩だと言えます。「早すぎた」「失敗した」といった評価が目立つ一方で、2022年現在でもサービスが存続しており、各コミュニティでイベント会場やコミュニケーションスペースとして利用されています。
本記事では「Second Lifeは成功なのか? 失敗なのか?」といった評価をするのではなく、実際に起きていた具体的なエピソードを取り上げつつ、現在の「メタバース」と比較します。
かつての「Second Life」ブームと現在の「メタバース」ブームは何が共通しているのか? あるいはどういった部分が違っているのか。両者を比較することで、現在の状況をよりクリアに捉えられるはずです。
今回お呼びしたのが、2008年(Second Lifeブームの当時)に「メタバース協会」を設立し、理事長として活躍された杉山知之先生(デジタルハリウッド大学 学長)と、「Second Life」の国内ブームの火付け役の渡邊信彦氏(Psychic VR Lab 取締役COO)です。
当時のことをよく知るお二人の対談を通じて、私たちが今後つくっていくべき「メタバース」のあり方について考えます。

杉山知之
デジタルハリウッド大学 学長/工学博士
87年よりMITメディア・ラボ客員研究員として3年間活動。90年国際メディア研究財団・主任研究員、93年 日本大学短期大学部専任講師を経て、94年10月 デジタルハリウッド設立。2004年日本初の株式会社立「デジタルハリウッド大学院」、翌年、「デジタルハリウッド大学」を開学し現在、学長。2011年9月、上海音楽学院(中国)との 合作学部「デジタルメディア芸術学院」を設立、初代学院長に就任。XRコンソーシアムアドバイザー、エンターテインメントXR協会監事、超教育協会評議員を務め、福岡県Ruby・コンテンツビジネス振興会議会長、内閣官房知的財産戦略本部コンテンツ強化専門調査会委員など歴任。99年度デジタルメディア協会AMDアワード・功労賞受賞。

渡邊信彦
Psychic VR Lab 取締役COO
東証1部上場 大手Sierにて金融機関のデジタル戦略を担当、2006年執行役員、2011年オープンイノベーション研究所 所長 を歴任、セカンドライフブームの仕掛け人としてメタバースのビジネス開発に関わる。その後、起業イグジットを経て、Psychic VR Labの 設立に参画。2017年2月取締役COO就任。他に事業構想大学院大学 教授、先端技術オープンラボSpiral Mind パートナー、地方創生音楽フェス「one +nation」のFounder などを務める。
「Second Life」の何が衝撃だったのか?

(撮影地:Gaalthyr ~ Sponsored by Jeanette’s Joint & Scarlet Fey, Gaalthyr –)
――まずは、これまで「Second Life」とどのように関わっていたかをお伺いできればと思います。
杉山:
「バーチャルリアリティ」は僕のずっと好きなもので、80年代から研究などを続けてきました。Webの時代に入ってからはWeb3Dというムーブメントが起こり、その次にブームとなったのが「Second Life」でした。
「Second Life」を見た三淵啓自先生(デジタルハリウッド大学 教授)や当時の(デジタルハリウッド大学の)大学院生たちはすぐにアメリカに行って、「なにかおもしろいことをやりましょう」と言ってきました。そこで僕らも会社で島を買ってみたのです。当時は月々でも結構な値段でしたね。そしてみんなで集まり、なにもない開拓地に家を建てるところから始めました。
一番驚いたのは、「リンデンドル(※1)」というお金があったことです。まだ「仮想通貨」という概念もない時代に、「Second Life」の中だけで通じるお金というものがあって、なおかつ両替所もあり、本物のドルになる。そこに惹きつけられましたね。もしかして儲かるんじゃないか……と。

(※1:「Second Life」で利用できる仮想通貨。リアルマネートレードが正式に実装されており、バーチャル空間上で衣服や土地などの売買ができる)
渡邊:
私は当時、金融機関のSIをやっていました。ちょうど「金融ビッグバン」が起きた頃で、金融機関がインターネットに参入し始めていた頃です。そんな中、みずほ銀行の方と一緒に、フィンテックイベント「Finovate」の第一回目を見に行きました。
その時に隣に座っていた人が「面白いところがあるから行こうぜ」と言って連れて行ってくれたのが、リンデン・ラボ(※Second Lifeを運営している企業)です。そこには創業者のフィリップ・ローズデール氏もいて、「ここで俺たちは島を作って、子供達に仮想のお金を渡して、ゲームを作らせて、お金の教育をやるんだ」と語ってくれたんですよ。それを聞いていたみずほ銀行の方に「絶対にやりたいから手伝ってくれ」と誘われたのが、「Second Life」との関わり始めです。
当時「Second Life」を見て一番面白いと思ったのは、やはり「リンデンドル」です。クリエイターにきちんと収益が配分される仕組みが既に備わっていて、作った物にスクリプトを組み込むと、それをデザインした人などへの収益配分を設計することができました。
私はその仕組みを利用して「モンスターカード」というカード会社を作りました。そこで、仕入れたアイテムの売上の一部をプールするようにして、たまったポイントに応じて、特定の人しか入れないロイヤルラウンジを作ったり、会員制度を作ったりしていました。
もちろん現在と異なる点も色々とありますが、いまNFTでやられてることの一部は、既に技術的には実現していたと言ってもいいと思います。「Second Life」という閉じた世界の中では、簡単に経済圏を作ることができました。ユーザーにとっても、公開されているアセットを利用するだけなので、むしろいまより簡単な部分もあったかもしれません。
――お二人の接点もお伺いしてもよろしいでしょうか?
杉山:
2008年に設立した「メタバース協会」の会員を募っていた中で、(渡邊さんへ)コンタクトさせていただきました。
メタバースの中に生活があり、住民がいると、様々な問題が起きます。「Second Life」の中だけで解決すればいいものもあるけど、やはりお金が絡んだりすると、税金の問題なども生じてしまう。「メタバース協会」を設立したのは、「Second Life」に可能性を感じている人同士で横につながり、話し合い、有事の際に組織として対応できるようにしたかったからです。例えば経済産業省が「『Second Life』に関する問題について、どこと話をつければいいの?」となったときに、社団法人があればみんなの役に立つのではないかと。
渡邊:
当時、「Second Life」関係者の交流の場はバーチャルにしかなかったので、リアルでも交流できる場を作っていただけたのは非常にありがたかったです。メタバースをテーマにしたカンファレンスも何度か開催しましたよね。
――昨今のメタバースブームは、当時の出来事を同じようになぞっている部分も多いように思います。
杉山:
当時は電通が「Second Life」に可能性を見出して、電通の動きに合わせてフラグシップ企業が一気に集まり、いろんな取り組みがなされましたが、結果を急ぐものだから、そこでつまずいてしまいました。
渡邊:
一気に引いていきましたね。当時、256m四方の土地がたしか2000ドルくらいで、それを分割して貸したり売ったりする流れがありました。電通はそれを9個ほど購入して、他社に貸していました。しかし、巨額を投じて作ったものの、それを体験するためにはある程度のグラフィックボードを積んだPCが必要でした。スマートフォンでも動作しなかったので、とにかくユーザーが少なかったんです。
取り組んでいた企業側では、ワールドごとに来場者数、滞在時間、注視されていた箇所などをマーケティング目的で分析していたのだと思いますが、その結果がだんだん落ち込んでくると、あっという間にみんな撤収してしまい、荒野だけが残ってしまったという……
閑散とした街を見ることが非常に多かったです。いまも「バーチャル○○」という空間って、イベント開催時以外は人が集まっていないと思うんですよね。それと同じことが常に起きていました。
杉山:
「車の自動販売機」とかがあって面白かったんですけどね。大きなタワーが立っていて、そこから新車が出てきて、実際に乗れたんですよ。
――当時参画した企業の「熱してから冷める」までの期間はどのくらいだったのでしょうか?
渡邊:
2006年から2007年ぐらいが大きなピークだったんじゃないんですかね。
杉山:
ざっと1年間くらいですね。
渡邊:
一方で、伊勢丹さん(※「REV WORLDS」)や日産さん(※VRChat「NISSAN CROSSING」)は、今もバーチャルワールドを展開していますよね。当時参画していた企業は、今回もメタバースに参画しているようにも見えます。
「Second Life」では収益フローがあらかじめ整備されていた

(撮影地:Kowloon)
――続いて、「Second Life」と現代の「メタバース」の共通点、あるいは差異についてお伺いします。技術的な観点はもちろん、社会的、文化的な観点など、様々な観点からお聞かせください。
杉山:
海外のクリエイターが「Second Life」の中で色々な小物を作ったら、1年間で1億円儲かったみたいな話が出てきて、そのニュースが世界中の人を惹き付けました。日本だと電通さんなどが大きな動きを見せていましたが、その陰に隠れて多くの個人クリエイターが「Second Life」を楽しんでいたのも事実なんですよね。

(撮影地:Sakura Matsuri 2022)
渡邊:
私の友人の台湾のクリエイターは、当時洋服ブランドを立ち上げて、月間の売上が250万円くらいに届いてました。他にも音楽方面では、月収が2〜3万円くらいのピアニストが「Second Life」で1回ライブをやるごとに、3000〜4000ほどのリンデンドルチップを得ていましたね。彼は「Second Life」でのライブを休日にやってたんですが、そちらの収入の方が多かったみたいです。クリエイターにとっては、新しいキャッシュポイントになるんじゃないか、という期待があったのだと思います。
今後はアセットの売上も大きくなっていくでしょうし、クリエイターがちゃんと報酬を得て、モチベーションを保てる世界はまた実現すると思います。それを仮想通貨でやるのか、法定通貨でやるのか、といった問題はありますが、とても面白い世界になるはずです。
杉山:
でも、当時流行らなかった原因でもある「その環境を楽しめるPCを持ってる人が少なかった」というのは、まだ未解決の問題としてあると思いますね。メタバースで活動するアーティストは、それを見に来る人が増えれば成り立つけれど、当時はそういう人が増えなかった。街は広大なんだけど、歩いていて寂しいというね。
――現在のメタバースプラットフォームではまだ、「Second Life」ほど収益フローの整備が進んでおらず、クリエイターエコノミーに関する具体的な事例も少ないように思います。これはなぜでしょうか?
杉山:
リンデン・ラボが「Second Life」を始めた際に持っていたコンセプトが「子供たちにお金のことを教えたい」だったからだと思います。
渡邊:
初めから仮想通貨ありきで作られていましたよね。著作権まわりも完全に整備されていましたし、誰が作ったものなのか全部履歴が残りました。アイテムをクリックすると作者情報が表示されて、さらにその人のショップまで全て辿ることができました。街で気になった物があれば、それを作った人にその場でコンタクトできて、仕事の発注までできたんです。
私も、初めて会社の社屋を建てる際に、かっこいい家具を作っているドイツ人の二人組のクリエイターに70万円くらいで発注してみたことがあります。発注した後、彼らのオフィスへ行き、アバターを介して「どんな風にしたいんだい?」などと会話しながら依頼できたのは画期的でしたね。
――履歴が残る仕組みはまさにブロックチェーンにおける台帳に通ずるものがあります。こうした機能は、ローンチ時点から搭載されていたのでしょうか?それともアップデートにともなって増えていったのでしょうか?
渡邊:
著作権とお金の仕組みは最初からありました。リンデンドル・スクリプトも最初からあったかと。
――となると、立ち上げの時点で、現在のメタバースとはかなり異なるのですね。
渡邊:
現在だと、同じような試みはNFTを用いて行われているのかもしれません。「VRChat」のようなメタバースは逆に「NFTを扱わない」と宣言していますが、それはコミュニティベースのプラットフォームだからなのかなと思います。
ただ今後、NFTやブロックチェーンがメタバースとうまく融合してきて、クリエイターネットワークへのキャッシュフローが整備されることで、より使いやすくなったり、社会的にも共感ベースのコミュニティが生まれていくのではと思います。そこまでくれば、「Second Life」とリンデンドルに閉じていた時代から先に進めるのかなと。
アバターで体験する「眠れない文化」

(撮影地:Sakura Matsuri 2022)
――スマートフォンとSNSが人とのつながり方や生活スタイルを大きく変えたように、その時代に普及しているテクノロジーは人々の価値観に大きな影響を与えます。現在の「メタバース」ブームは、「Second Life」ブームの当時とはデバイスの性能も普及しているコンテンツの種類も大きく異なります。こうした社会的な背景の違いは、プラットフォームの使われ方にどんな違いをもたらすと思いますか?
杉山:
「Second Life」が流行した当時、ほとんどの人にとって「自分のアバターを作る」ということは初めての体験でした。本来の姿でない自分になるとか、いつもと違う服を着てみるといったことが、すごく新鮮だったんです。
渡邊:
「VRChat」が出てきた今だと、VRデバイスを用いて没入し、アバターとして会話をするコミュニティがベースにあると思うので、出発の思想はちょっと違うかもしれませんね。
当時の「Second Life」は、動画サイトで例えると「Youtube」より「ニコニコ動画」の雰囲気に近くて、「そこで儲かっている」ってことがあまりかっこよく思われなかったように思います。一方でいまNFTは、NFTアートの「Bored Ape」のアイコンをつけていたら「かっこいいねキミ!」って言われるなど、コミュニティとセットで機能している面がある。そうしたファッション性やブランディング、文化的な面は「Second Life」の頃とは大きく違うと思います。
杉山:
著作権についてもみんな素人でしたね。街ができあがったときにスナップショットの撮影をすると、写り込んでしまった人から抗議がきたものの、「街だから写り込んでもしょうがないよね?」となったり……そのためのルールすらない時代でした。はじめてメタバースに入って、みんなであたふたしていたのが「Second Life」の時代です。
あと、夜な夜な人が集まるスナックもありましたね。仕事から帰ってきて、夜中にみんなで集まり、朝まで入り浸っているような。そういう「眠れない文化」でもありました。

(撮影地:Cafe Grotto)

(VRChatワールド「ポピー横丁」)
――そこは現在のソーシャルVRと同じですね。「VRChat」ワールドやコミュニティで早い段階で表に出てきたものといえば、やっぱバーやスナックだったかと思います。最近はヘッドセットを装着したままみんなで寝る、という文化もあります。
渡邊:
本当に同じですね(笑)。
今も続く「Second Life」独自の文化
――当時の「Second Life」は、現実の自分や社会と地続きにあったものだったのでしょうか? それとも、匿名になって生まれ変われるような場所だったのでしょうか?
杉山:
双方がごちゃまぜでした。ただ、本名を明らかにしている人の方が少なかったはずです。とはいえ、みんな「Second Life」の中では超かっこいい住宅に住んでいましたね。現実はともかく、ハイライフなんですよ。
渡邊:
グラフィックも良かったですね。写真撮影する際のぼかしや、ムービーを撮影する際の照明の仕組みとかも全部販売されていたので、買ってしまえば映画なども簡単に作れました。使い勝手も良くて、「STYLY」を立ち上げた際に「Second Life」でハッカソンを開催して、開発の参考にしてもらったほどです。
杉山:
「Second Life」で映画を作るのも流行りましたね。
渡邊:
「Machinima」ですね。ミュージックビデオなんかもすごいきれいに制作できて、特にume sibさんが作っていたものは10年以上前に撮ったものとは思えないほど、映像のクオリティが高いんですよ。
――「VRChat」でもカメラ機能が大幅にアップデートされ、クオリティの高い写真が撮れるようになりました。それによってSNSでの拡散がされやすくなったり、映像制作に取り組む人や演劇をやる人も出ていますね。
渡邊:
ちょっと、私の好きなMachinemaビデオ流してもいいですかね? しびれますよ。
――これが10年前の作品ですか……!?
渡邊:
そうです。ぼかし効果とかカメラ操作とかも全部「Second Life」でやっています。原付もリアルタイムに運転(操作)していて、何度かリテイクしているはずです。
――これが1万再生されていないところに「なんとかしなければ」と思わされますね……!
渡邊:
再生数が少ないのは、日本の「Second Life」ブームは2009年ぐらいには去ってしまい、2012年は既に廃れた後だったからでしょうね。でもume sibさん、14年前から投稿を始めて、今でも活動を続けられているんです。最新の動画投稿は数日前です。趣味でやっていると思うんですけど、本当にすごいなと思います。
(ume sibさんが今年の4月23日に投稿した動画)
――音楽のCDと同じで、「いい曲が必ずしも売れるわけじゃない」と似たものを感じました。クリエイティビティは申し分ない。けれどもみんなが見てるわけじゃない。どうやってその壁を乗り越えればいいのかと考えてしまいます。
渡邊:
いまでも「Second Life」を続けている人は、どうすればいい映像が撮れるのか、どんな風に過ごしてきたのか、それこそ揉め事にどう対応するのか、蓄積しているノウハウがあるはずなんですよね。世代こそ違えど、通ずるところはあるはずなので、壁を超えるべく現在のメタバースの住人と交流していければいいのになと思います。
――ちなみに渡邊さんはいまでも「Second Life」をプレイされているのですか?
渡邊:
プレイしています。月に1回友人がライブをやっていて、土曜日の夜に行ってチップを入れに行っています。
杉山:
「Second Life」は未だに生き残っているのがすごいですよね。
渡邊:
未だにアクティブユーザーが100万人くらいいますからね。
――当時「Second Life」を使っていたのは、先端技術に関心のある人だけだったのでしょうか?それとも多くの一般の人も利用されていましたか?
渡邊:
どうでしたかね……ただ、日本だけでアクティブユーザーは30万人と言われていましたね。
杉山:
普通にニュース番組とかで取り上げられていましたからね。
渡邊:
日テレの土屋(敏男)さんとか、シャ乱Qのはたけさんなどもやっていました。
杉山:
はたけさんとはいろいろ交流がありましたね……!
渡邊:
はたけさんは「Second Life」でプロダクションを作って、「トマーレコード」というタワーレコードを模した黄色い看板をいっぱい出してました。私はそこでレコードを出していました(笑)。MP3をダウンロードできるだけだったんですけど、しっかり販売してお金が入る仕組みがあったりしました。(1曲)100円ぐらいなので、みんなジャケ買いして、音源を聴いていましたね。
今では、PCが高性能になり、スマホでも動くようになってきているので、面白い文化作りができれば、当時できなかったことが定着してくるんじゃないかと思います。
現代にも活きる「Second Life」の知見とは

(撮影地:Sakura Matsuri 2022)
――当時おふたりが、バーチャルな生活を実践していた中で得られた知見や、失敗談や成功談などはありますか?
杉山:
私は、やはりアバターですね。私はいくつかアバターを使い分けて活動をしていたのですが、「アバターになりきる」ことによって「普段の自分とは違う自分」を発見できるのが面白かったです。
もう一つ、普段忙しくしている中で、アバターだけ高級リゾートの海岸に寝そべったままにしておくと、現実の自分も癒やされる感覚を覚えたことがありました。アバターに可能性を感じた瞬間です。
つまり、メタバースをみんなが簡単に使えるようになると、肉体としての自分以外の自分も表現できるようになる。「1つの道」と言われがちな人生を、4本や5本の道で歩いていけると思ったんですよ。そういったことが(昨今の)メタバースでもできるんじゃないかなと。それが、私が「Second Life」で過ごした濃い2年間で得たことです。
物理的に移動することなく「解放された空間」に行ける。なんてたって「Second Life」では空を飛ぶことができますからね。

(撮影地:Ellingson National Forest)
渡邊:
アバターの影響はすごく大きいですよね。「アバターの服って商売になるの?」といった議論には賛否両論がありますが、常にバーチャル空間で過ごして、その生活の価値が高まってくれほど、アバターの服に凝りたくなるんです。夏にコートを着ているのが恥ずかしくなるんですよ。
前回のブームでは、バーチャル空間で仕事や遊びなどのさまざまな場面に合わせてアバターを着替えることが、当たり前のものにはならなかった。アバターの服は、現実で「今日は出かけるので洋服をちょっと替えよう」と思うのと同じようには受け止められなかった。そういったことを実践しているのは、一部の熱狂的な人たちだけでした。
――アバターの服を着替えることが価値になるような体験や文化を作れるかどうかが重要になりそうですね。高品質な服の3Dモデルを制作するのも重要ですが、それ以上に、コミュニティやイベントなど、人々を駆り立てる「着替えたくなる理由」をどう作っていくかがポイントになりそうです。
近年はコロナ禍ということもあり、「必ずしも現地に行く必要はない」という感覚が普通になりつつあります。だからこそ、アバターでのコミュニケーションも受け入れられやすいはずです。その感覚がさらに浸透してくると、例えば(バーチャル空間での)飲み会に行くときに「いつもと同じスーツアバターで行くのは嫌だなぁ」と思うようになるかもしれません。そうした気持ちが芽生えた人は、300円とか500円の私服を買うようになりますし、もしかすると1000円以上出すかもしれない。
そうした流れから、クリエイターへのキャッシュフローの成立や、クリエイターの育成、事業の成立などの議論に発展していけば、「Second Life」を超えてくると思いますね。
杉山:
私は、若い時からコンピューターで3Dをずっと扱っていたから、どうしても最後は「そこの空間に行きたい」って思ってしまうんですよね。今はこんな病気(※)になっちゃって、現実ではもう歩けなくなっちゃったもんだから、余計に、早いところアバターになって、向こうに行って飛んだり跳ねたりしたいんですよね。
高齢化すると、みんな100歳まで元気なわけじゃないから、そういうメタバースの利用価値も出てくると思います。その時、「若いときの姿がいい」という人もいるでしょうし、逆に、20歳くらいの子が100歳ぐらいの顔になりたいということもあるかもしれない。年齢や性別から自由になれるんですよね、メタバースって。
ロシアのウクライナ侵攻などを見てても思いましたが、やっぱり現実世界ってすごく窮屈なんです。いろんなことがお互いに関連しすぎてしまっていて、自分勝手には生きていけない。そうした時代で、人々の一つの受け入れ先として、メタバースがあるんじゃないかと思います。ありとあらゆる時代や文化を吸収できるのがメタバースのいいところですから。
(※ 参考:杉山先生の健康状態について)
渡邊:
あまり人には言いませんが、私は女子アバターと男子アバターの両方を持っていて、女子アバターを使ってモデルとして活動していたんですよ。ファッションショーに出演して、それでお金をもらったりしていました。「現実ではできないことができる達成感」みたいなものはやっぱりありますよね。その価値観は今後ますます強くなると思います。
これまでは中央集権的な雰囲気で、(中心に立つ人が)「これが正しい」って言ったらみんながそれに従わなきゃいけなかった。しかし今では、「僕はやらないけど、君がやっていることはいいと思う」と、それぞれの意見が分散化しつつあります。となると、やりたいことを実現する方法はたくさんあった方がいい。
一方で、当然それを認めない人たちも出てくるはずです。しかし、それはそれで良くて、ちゃんと技術を活用できて、その価値観を認める人たちの中で経済を回していければ、それで一つの世界ができあがるはずです。
――「Second Life」が流行した当時を知る者として、現在のメタバースブームに対してどういうスタンスを取り、何をしていきたいかを教えてください。
杉山:
基本に立ち返って、アバター文化に注力していきたいです。いまは、うちの学生全員にアバターを持ってもらうところから始めています。それもTPOに応じて2〜3種類持つようにする。そしてまずは「Zoom会議にアバターで出席する」といった軽いところから始めてもらう。「自分の顔は見せたくないけど、アバターで出るならいいよ」って学生は結構多いので。
アバターを所持して、色んなメタバースへ行く体験を積んでいく中で、何人かはハマると思うんですよ。そうしていく中で、自然といくつかの大手メタバースが残っていって、新しい「中心」が見えてくると思います。「アバターをみんな持とうよ」というところからコツコツとやっていきたいですね。

(撮影地:Chiba Industrial District)
渡邊:
私は前回ハマったときに、特に象徴的に「これだ!」と思った出来事があります。
当時、吉祥寺に住んでいて、会社の帰りにある焼き鳥屋さんによく通っていました。ただ、私はあまり飲めない方なので、焼き鳥を買って持ち帰っていました。そんなある日、「Second Life」上にその焼き鳥屋の支部が作られたのです。それ以降、私が焼き鳥を持ち帰ってから「Second Life」に入ると、先ほど焼き鳥屋にいた人たちが続々とやってくるようになりました。
そうした生活の中で、バーチャルの焼き鳥屋にいた人に「(リアルの店舗に)おいでよ!」と誘ったら来てくれたり、逆にさっきまでリアルの焼き鳥屋にいた人たちが「Second Life」にログインしにきてくれたり……リアルとバーチャルが融合した瞬間の感動は、非常に大きかったです。
「バーチャルに来てください」と言って抵抗なく来てくれるような人だけだと、またブームは失速し、失敗すると思います。鍵となるのは「リアルの生活の中にどうやってメタバースとの接点を作っていくか」でしょう。
「STYLY」ではそのために「リアルメタバース」という考え方を掲げています。都市とデータをつなぎ、都市の中でホログラムやXRグラス越しに情報などが現れれば、それこそバーチャルとリアルが本当に融合した形になるはずです。
「ホームページなんて使わないぜ!」と言っていた人も、今やホームページを作らなければ商売ができないのと同じように、メタバースにアバターを持ってないとコミュニケーションできないという時代がくるはずです。なので私たちは、都市の中でメタバースを開いて行きたいと思っています。
杉山:
私はいま専門家を集めて、大学のバーチャルキャンパスを作ろうとしています。バーチャルキャンパスはリアルのキャンパスとつながっていますが、だからといって「リアルなキャンパス」をバーチャル空間に作っても仕方ない。だから「メタバースならではのキャンパス」をやりたいと考えています。
そして、感覚としてはやっぱり、自分のアバターがどのメタバースにも遊びに行けるのが一番いいなとは思ってます。
渡邊:
いま、各社が提供するメタバース同士が繋がる「オープンメタバース」が叫ばれていますよね。「Second Life」の時代からそうした動きはありましたが、今回は社会的な動きもあります。そして、多くのメタバースと同じように空間レイヤーにも来てくれるようになれば、現実とメタバースを行ったり来たりしたりしながら、デジタルのコンテンツで稼ぐクリエイターが生まれて、新しい価値観や社会が生まれるんじゃないかと思います。逆に、そこまでやらないと「Second Life」のブームの時代から正直変わらないんじゃないかと思いますね。
少し心配なのは、ユーザーにアプリをダウンロードをさせたくないからという理由から、WebVR・WebARに流れていることです。実現できることがWebで可能なことに限定されると「結局ライブ鑑賞などはYouTubeで見た方が綺麗だよね」といった空気になってしまうのではないかと。メタバースで実現できることの幅、それに対する期待を制限しないでほしいのです。いろいろなものを切り捨てるほどビジネスに寄っていきますが、同時に魅力も半減してしまいます。そうなってしまうと、「『Second Life』の方がよかったよね」って言われかねません。
――メタバースの文化が成熟するに従って、人と人とのしがらみも生まれてくるのではないかと思います。「Second Life」ではいかがでしたか?
杉山:
あったと思いますよ。なにせ「戦争をしない国」といったコミュニティがあったので。私は「バラ色の国」ができるなんて全く思ってなくて、コミュニティごとに倫理が掲げられていて、ここなら自分が居やすいと感じるメタバース――あるいは「小さな国」を、いくつか見つけて回って楽しむものだと思います。世界統一的な国ができるみたいなことは全然無くて、非常に細かくなるんじゃないかと思います。
渡邊:
全く同感です。「バーチャル空間で理想の社会を作ったところで、リアルは変わらないんじゃないか」って言う人もいると思いますけど、変わるんですよ。
杉山:
変わります。
渡邊:
アバターだろうが肉体だろうが、どちらも同じひとりの人間なんですよね。だから、バーチャル空間とリアル空間を同じレベルで扱えるよう、私たちは文化的に成長していく必要があると思います。昼と夜でアバターを使い分けたとしても、それぞれがお互いに干渉しない全くの別人格というわけではなく、同じひとりの人間に繋がっているという意味で「同一人格」であり、相互に連動した形になっていくといいなと思います。
杉山:
「メタバースの向こう側にずっと住んだらどうなるか?」っていう壮大な実験は、15年前の「Second Life」の住人が本当に大規模に参加して行われていたんです。「Second Life」の中で知り合って結婚した人ってたくさんいるわけだからね。「Second Life」の中では夫婦みたいなのでフラグ立てられるんですよ。
渡邊:
よく喧嘩して離婚とかしてましたよね。「家具の趣味が違う」とかね。
杉山:
現在では、XR技術のおかげで、現実とメタバースの境目がさらにわからなくなってきています。
――「Second Life」の時代に「境目がなくなった」と感じた体験には、どのようなものがありましたか?
渡邊:
やはり、リアルの生活とメタバースコミュニティが融合した時ですね。「Second Life」では一時期、会社を作って株式上場することができました。登記して上場することができ、市場も形成され、チャートも動いていました。今は無くなりましたけれど、そこまで精緻に作られていると、現実世界での経済活動となにも変わらなくなってくるんですよ。
時々「NFTとメタバースは、本質的には関係ないじゃないか!」と言う人がいますが、私は、NFTとメタバースはいずれ一緒になった方がいいと思っています。
NTFアート「Bored Ape」のすごいところは、裏にいるコミュニティですよね。Discordで展開されているコミュニティが素晴らしくて「そこのコミュニティに入りたいから、NFTを持ちたい」という人もいるほどなんです。まあちょっと高くなりすぎていますけど……。
「同じ思想を持った人たちが集まるきっかけ」として考えると、NFTも「Second Life」も「VRChat」も、目指すところは同じではないでしょうか。価値観が多様化していく中で、「同じ価値観を持つ人同士で何かをやる」ということです。物理的に離れていると難しいですが、バーチャル世界は繋がりやすく、アクションを起こしやすい。価値観が同じ人たちがコミュニティを作ると、ときには暴走するかもしれないけれど、ものすごくパワフルに動くことができるのです。その動きがリアルの世界とバーチャルの世界にも繋がるように進んでいって欲しいですね。
――登記や上場のみならず、市場の形成まで……。お話を聞くほど「Second Life」ではそんなことまでやられていたのかと驚くばかりです。
渡邊:
こうして語っていると「『Second Lifeオヤジ』うるせえよ 」って言われるんですけどね(笑)。当時ハマっていた人も、あまり当時のことを話したがらないんですよ。「あの時ホワイトペーパー作ってたじゃないですか? 著作権のやつとか出してくださいよ」と頼んでも、「俺たちが言うとさ、『Second Lifeオヤジ』うるせーよって言われるから、やめとくよ」と返ってきたり……。でも当時ちゃんと作ったものがたくさんあるんですよ。著作権の問題は当時からよく議論されていましたし、今でも通用するはずですけどね。
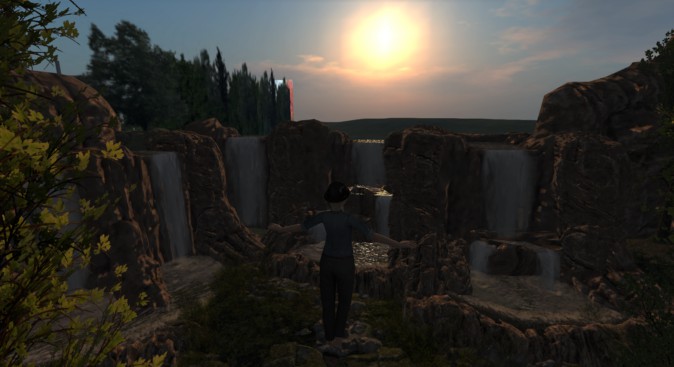
(撮影地:Ellingson National Forest)
――「同じ話を未だに議論している」という問題は日本だけでなく世界でも起きているような印象があります。
杉山:
一度広く当時の「Second Life」の関係者を集めて、全部覚えてることを語ってもらった方がいいですね。まだ現役でギリギリ残っているので!
――ぜひやりましょう! ありがとうございました!
「Second Life」へのアクセスはこちら。
https://secondlife.com/?lang=ja-JP
(聞き手:yunoLv3・すんくぼ、執筆:浅田カズラ・yunoLv3、編集:ゆりいか・水原由紀)
The post 【特集】歴史は繰り返しているのか?「Second Life」全盛期の仕掛け人たちが語る appeared first on Mogura VR.