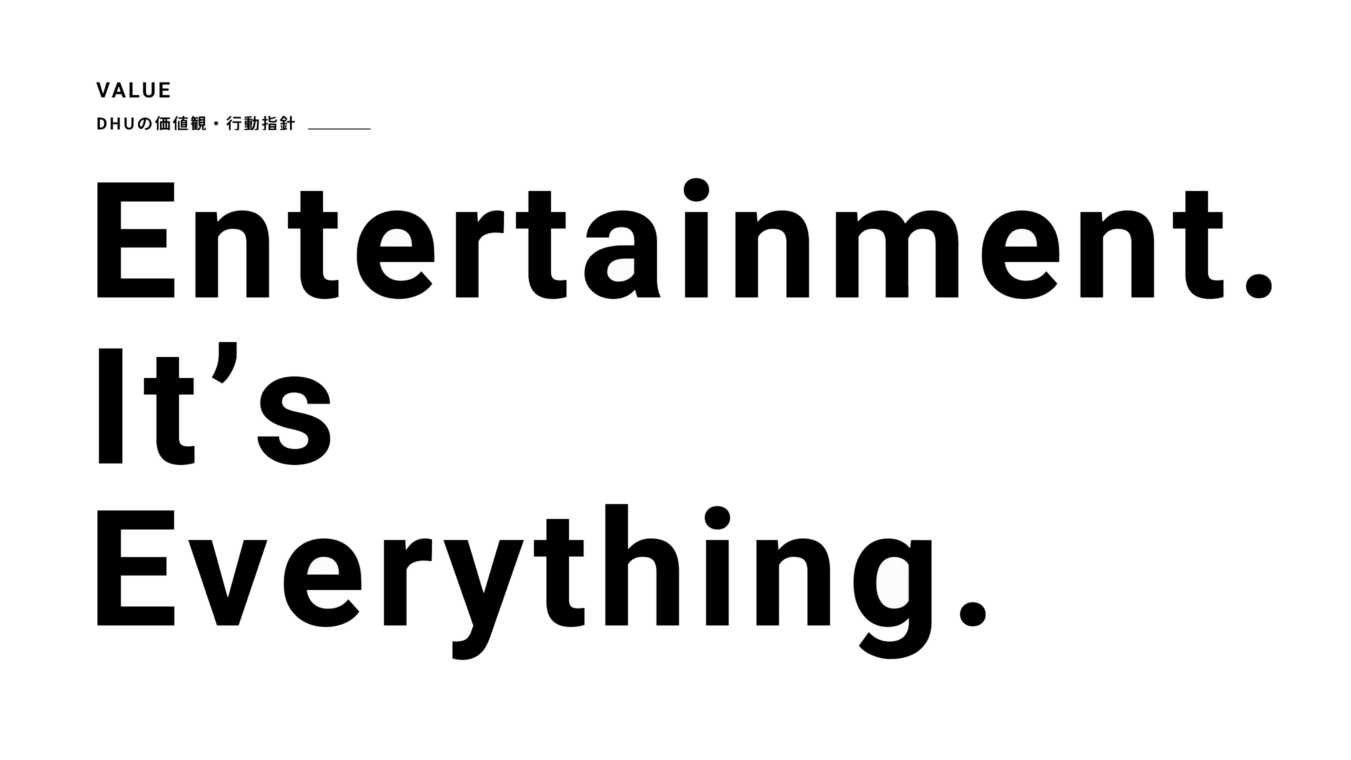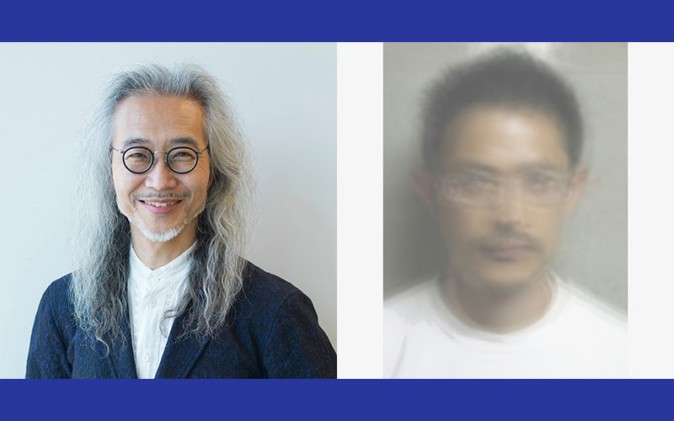「バーチャルキャンパス」と聞いて何を思い浮かべるだろう。今ある学校をそっくりそのままVR空間に移植したデジタルツイン、あるいは空に浮かぶ巨大建築だろうか? 教育における「バーチャル」の活用は遠隔授業や体験学習において進んでいるものの、バーチャルキャンパスという「学生や教員が交流し、学び、出会う場所」を作る取り組みにおいては模索が続いている。
折しも、これまでに数々のクリエイターを輩出してきたデジタルハリウッド大学では、バーチャルキャンパスの構想とプロトタイピングが進行中だ。本記事ではデジタルハリウッド大学学長の杉山知之氏と、『独学大全』『アイデア大全』などで知られる独学者・読書猿氏のセッションの様子をお送りしよう。
杉山知之 / Tomoyuki Sugiyama
1954年東京都生まれ。デジタルハリウッド大学 学長、工学博士。87年よりMITメディア・ラボ客員研究員として3年間活動。90年国際メディア研究財団・主任研究員、93年 日本大学短期大学部専任講師を経て、94年10月 デジタルハリウッド設立。2004年日本初の株式会社立「デジタルハリウッド大学院」を開学。翌年、「デジタルハリウッド大学」を開学し、現在、同大学・大学院・スクールの学長を務めている。2011年9月、上海音楽学院(中国)との 合作学部「デジタルメディア芸術学院」を設立、同学院の初代学院長に就任。XRコンソーシアムアドバイザー、一般社団法人Metaverse Japan理事、超教育協会評議員を務め、また福岡県Ruby・コンテンツビジネス振興会議会長、内閣官房知的財産戦略本部コンテンツ強化専門調査会委員など多くの委員を歴任。99年度デジタルメディア協会AMDアワード・功労賞受賞。著書に「クール・ジャパン 世界が買いたがる日本」(祥伝社)、「クリエイター・スピリットとは何か?」(電子書籍、ちくまプリマー新書)、『デジタル・ストリーム ― 未来のリ・デザイニング』新装版(電子書籍、デジタルハリウッド・パブリッシャーズ)ほか。
読書猿 / Dokushozaru
ブログ「読書猿 Classic: between/beyond readers」主宰。「読書猿」を名乗っているが、幼い頃から読書が大の苦手で、本を読んでも集中が切れるまでに20分かからず、1冊を読み終えるのに5年くらいかかっていた。
自分自身の苦手克服と学びの共有を兼ねて、1997年からインターネットでの発信(メルマガ)を開始。2008年にブログ「読書猿Classic」を開設。ギリシア時代の古典から最新の論文、個人のTwitterの投稿まで、先人たちが残してきたありとあらゆる知を「独学者の道具箱」「語学の道具箱」「探しものの道具箱」などカテゴリごとにまとめ、独自の視点で紹介し、人気を博す。現在も昼間はいち組織人として働きながら、朝夕の通勤時間と土日を利用して独学に励んでいる。『アイデア大全』『問題解決大全』(共にフォレスト出版)はロングセラーとなっており、主婦から学生、学者まで幅広い層から支持を得ている。『独学大全』は3冊目にして著者の真骨頂である「独学」をテーマにした主著。なお、「大全」のタイトルはトマス・アクィナスの『神学大全』(Summa Theologiae)のように、当該分野の知識全体を注釈し、総合的に組織した上で、初学者が学ぶことができる書物となることを願ってつけたもの。Twitter: @kurubushi_rm、プロフィールイラスト:塩川いづみ
学校の「いいところ」「悪いところ」は表裏一体
杉山:
私は40年以上教員を続けているがゆえに、「学校って良いものだよね」と漠然と思ってしまっているところはあります。しかし、学び舎たる学校が果たしている役割、そして学校でなければならないことをまだ突き詰められていないとも考えています。
今はコンピュータがあり、私たちはソフトウェアによって作り出されたものを、空間や生活の場と同じように認識できるところまで来ている。通常のリアルな空間では作り出すことが難しいような、変幻自在の人工環境を作れる時代です。では、そもそも「学びに適した人工環境」とは何か。学びたくて来た人に、学校が与えられるプラスの意味とは何なのか。そして、もっと学びたくなるようにするにはどうしたらいいのか——といったことをさらに考えたいのです。これらをぐるっと含めて、人工環境として理想的な学び舎が作れるとしたら、読書猿さんはどこにポイントがあると考えるのかを知りたいです。
読書猿:
最初に正直なことを言うと、僕は学校があまり得意ではないんです(笑)。 なので「仕方なく」独学していた側面は多分にありますね。一方で、独学を続ける中で学校のすごさを思い知りました。周りに誰かがいて、一緒に色んなことを学べる環境が制度的にも物質的にも作られている。これは凄まじく工夫され、積み上げられてきたものだと思うのですが、同時にこの工夫は僕が「学校って苦手だなあ」と思わされた部分でもあります。
そもそも人間という生き物は気が散りやすい。では気が散らないようにするにはどうすればいいか。一人ひとりに個別指導するとコストがすごい。では一度にたくさんの人に知識を伝えるにはどうしたらいいか……といった前提や制約から、教室のレイアウトや学校のシステムはできあがっている。ただ僕は気が散ったら散ったで、そっちの方に行きたくなるので(笑)、苦手なんです。
それから、授業は50分や90分といった時間でひとつひとつ区切られている。そして授業が終わると、大抵の場合はまったく関係ない別の分野の授業が始まってしまう。同じことを何時間もやっていたい性分なので、この「突然切られる」のがイヤだったわけですね。
しかし「いろんな人が一同に会して何かをする」というのは学校における大きなポイントです。当たり前ですが、僕みたいに何日でも同じことを続けられるし続けていたいという人と、そうでない人がいます。そうすると学ぶうえで必要な注意が途切れないように、でも適度に打ち切れるような形で授業の時間が決まっていく。授業にも様々なやり方があると思いますが、なんだかんだで時代の淘汰をくぐり抜けて生き残ってきたやりかたなんです。僕は、これがベストだとは思いませんが、注意力の続かなさのような、人間の弱点をカバーするしくみとして、学校って思っていたよりもずっと作り込まれていると思うんです。ただし、学校にいた僕が苦手だと思っていた部分は、この「よくできた学校のしくみ」と表裏一体なんですよね。だから難しい。
しかし、先ほど杉山先生が言われたような、物質的なレイヤーのうえにコンピュータでいろいろなものを実装できるとなれば、一人一人の認知特性に合わせた環境を作れるようになる。まだまだ研究開発が必要な箇所はたくさんあると思います。でも、もしかすると僕が苦手だったところをうまくケアできるような、それぞれの人にフィットするような学校のあり方は可能かもしれない。たとえば先生は一人だけど、生徒が見聞きしている環境や状態が全部違う、といったあり方の可能性は探っていくと面白いと思うんです。ここはまさにこれから模索する、あるいは今、杉山先生のような方々によって模索されつつあるのかな、と。
僕が『独学大全』を書いた動機のひとつが、今話したようなことなんです。「あらゆる人にとって、ベストなひとつの方法があるぞ!」という本じゃなくて、「あなたにはAとBがいいかも。君ににはBとCが……」みたいに、それぞれの人が自分に合わせた学び方ができるように、使えるツールを取り揃えた道具箱のような本を作りたかった。「理想のやり方」ではなく、多様性を許容するような。そのせいで、あれだけ分厚くなってしまったんですが。
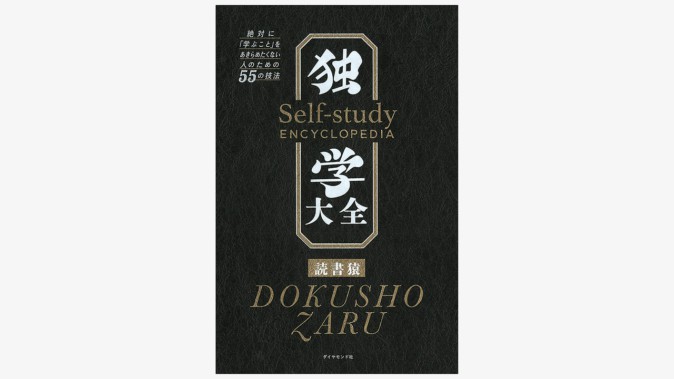
(読書猿氏による『独学大全』。独りで学ぶためのあらゆるメソッドを集約・分類・整理した、788ページの大著だ)
学ぶ=「知のネットワークに入っていくこと」
読書猿:
「学校」というテーマからは少し脱線してしまいますが、「学ぶとは何か」という問いについての僕なりの回答は、「知のネットワークの中に入っていく」ことだと思っています。例えば『独学大全』の著者は僕ですが、あの中で紹介した技法のほとんどは、それから説明に使った概念やアイデア、もちろん「日本語」や「文字」だって僕が自分で開発したものじゃない。いろんな人達が書き残したもの、その人たちもまた別の誰かから学んで来たものを集めた本です。そこには先代、先々代……という知的営為の積み重ねがあり、そのネットワークや流れ、あるいは歴史に参加することが、学ぶことなのだと。
一般的には「何かを自分の脳に入れる(インプットする)こと」が学習だと思われていますが、そうではなく、むしろ自分の方が知のネットワークに入っていく(参加していく)ことこそ、学びなのだと思います。「インプットする」、「頭の中に入れる」と言うと記憶や暗記をすればいいということになりますが、それは知識を「モノ」として扱ってしまっている。「書かれたモノ=知識」というイメージが強固にあるせいか、倉庫に入れたり積み上げたりするような感覚で知識を「モノ」として扱って、知識が「所有」できるなんて勘違いしてしまう。でも人間が学んだり知ったりすることは脳に何かを積み上げていくのではなく、脳のネットワークを組み替えるようなものなんです。だからこそ何かを知れば、ものの見方や考え方が変わってしまう。知識は「モノ」ではなく「コト」です。
そして知識が「コト」なのだとしたら、それはどこかに蓄えられるようなものではなく、自分自身を作り変えることでその営みに参加し、つながっていくことをずっと繰り返すのだと思います。もちろん、ここでいう知識は、書物に代表されるような、言語化できるものだけではない。身体的に学ぶ徒弟制的なものにも秩序や工夫の蓄積があるように、知の営み、そして知識がある。最初はよそよそしく見えるものに少しずつ参加しながら、慣れながら、染み込ませながら、身体化しながら参加してゆく。そうして知識を「コト」として実践できるようになるのが、学ぶことなのだと思います。
これは「独学」は「孤学」ではないという話につながります。独学とは一人で知識を「モノ」として取り込む行為ではなくて、たとえ一人で本を読んでいても、その書物や読むことを介して、誰かと繋がり合っていくようなイメージとして、僕は捉えています。だって一冊の書物がこの手に届いたそのことが、たくさんの知的営為がこの世界に途切れずつながってきた証拠じゃないですか。ひとつの知識の中にも扉がたくさんあって、その扉を開けるとまた無数の扉が……とずっと続いていく。これが学ぶことのイメージです。そう考えると、こうした学びが行える環境を、自分の中や周囲の外部足場として作ることそれ自体も、学びの不可欠な一部だよ、という話を誰も書いてくれないから『独学大全』があんなに分厚くなってしまったんですが(笑)。
杉山:
大変よくわかります(笑)
「励ます人」「支える人」としての教師
杉山:
そしてこれは「点から線、線から面」という話でもあるわけですよね。デジタルハリウッドに来る学生はそもそも自由な人が多く、自分がやりたいことをなんとか上手くできるようになりたい、という人が多いんですね。最初は点で入ってくるけれど、好奇心が強い人が多くて、いずれどんどん線、そして面へと広がっていくんです。
そして学校という場には様々な先生がいる。人を「書物」、つまり知の結節点のひとつとみなすならば、読書猿さんのおっしゃっている「自分も知のネットワークに、ひとりの人間として入っていくんだ」という感覚は「本当にそのとおりだ」と改めて思うんです。学生たちがそれを意識できるような場にすべきなんだと。『独学大全』もそのように読みました。
読書猿さんが話していたような、「一人一人の認知形態の差異に応じて、その人なりの素晴らしい学習方法をコンピュータとともにできるようになる」というのは我々のような立場からするとひとつの理想形に思えます。究極の「独学」環境ですよね。
読書猿:
また少し脱線気味になるのですが、明治期に活躍したジャーナリストの宮武外骨のお兄さんで、宮武南海という人物がいます。彼は明治18年というかなり早い時期に、印刷業と同時に並行して学校を作ってしまうんですね。学校には毎年新しい学生が入ってきて、自分の会社で印刷した教科書を買ってくれるから。完全にビジネスからの発想なんです。しかも最初から「独習コース」、独学のためのコースがあった。学びたくても遠方に住んでいたり、仕事があったり通えない人がいる。そういう人たち向けて通信教育を受けるコースがあれば、南海が作って印刷した教科書を通学生以外にも更に売ることができるという(笑)。 こうしてリモートな学習環境を作り上げてしまった。当時、全国はおろか東京ですら「大学」の数は限られています。後に「早稲田講義録」として名を上げることとなる東京専門学校(早稲田大学の前身)の通信教育が始まったのが明治19年ですから、先駆的な試みだし、目の付け所がすごい。
おまけに南海も筆が立つので、毎号毎号、パンフレットを発刊するたびに独学者の人たちを励ます、激励する文章を書いていた。「独習」という言葉や自分の書いた文章を通して、学校には行かない、あるいは行けないけど学びたい、という人たちを、制度的にだけでなく、心理的にも支えていた。その結果、南海の印刷&学校という事業は大きく伸び、南海は紳士録に載るくらい経済的に成功しました。
杉山:
デジタルハリウッドでは卒業制作という形でアウトプットを出すことが必要になるのですが、毎年学生が大変そうにしているんですね。教える人は、その苦しみを励ます、支える、助ける——もちろん最後はその学生自身が自分のものにしなくてはいけないのですが——ということを行っている側面がある、とも言えますね。
一人だけなら「自分はここまで作れたな」で終わってしまうわけですが、学び舎や場があると、先生や仲間がいる。喜んでもらったり批評してもらったりすることで、自分がどこまで到達したのかが感じられる、わかる。そういう場所です。
誰が、知の山の、どこを担うのか
読書猿:
大学ってなんだろう、という話もありますよね。いわゆるユニバーシティ(University)の起原たる中世の大学は元々、学びたい人が集まったギルドでした。同じ職業や志向を持った人が、親方と弟子という徒弟制的な関係のもとに集団を形成し協力する。そうして領主や王、つまり権力者から「このギルドに関してはお前たちに任せる」という自由、自治の許可を取ってくる。このギルドを学びたい人、学習者たちが行ったのが大学のスタートで。修士課程がマスター(Master)なのはマイスター(Meister)、ドイツ語の「親方」なわけですね。
そして初期の大学は、医者や弁護士、神学者になるための専門教育が上位に据えられていました。その後「研究大学」がドイツで生まれて、これは研究者が研究を通じて教育する、やってきた学生も研究者の卵として迎えるしくみです。これは言うなれば「知識を作る側の人間を作る場所」としての大学で、教える側の技を見様見真似でやり、次第に馴染み、やがて評価され、知識を作る人としてなって卒業する。これによって知識を作る人がたくさん生まれたんです。やがて同じ「型」のようなものや系統を身に着けた人々がたくさん生まれると、学派ができてくる。そうした人が別の大学に行って研究をスタートし、教える人と学ぶ人のサイクルがぐるぐる回るんです。そしてサロンやアカデミー的なものは、言ってしまえば一点物、いわゆる「天才」のためのもので、弟子を取って続けていくためのしくみではなかった。誰かが脱退したり亡くなったりしてもアカデミーそのものは継続しますが、ある系統の弟子や学派を作っていくしくみではない。
同時に、「大学だけでいいのか?」という問いは20世紀から21世紀にかけて問われ続けています。そして今の日本の大学が、ギルド的共同体として動けているのかというと……大変ですよね。これまで培ってきた知的な資産が人と制度の双方で存在していて、それでなんとか持ちこたえている、といった構図だと思います。
独学者のわがままな意見ですが、大学はもっと元気でいてほしいし、すごく応援しています。そうすると独学者の環境もよくなりますし、スポーツでもそうですが、裾野が広ければ広いほど山は高くなる。大学は「高級なことを教えてくれるところ」ではなく「作る人を作るところ」ですから、作っている姿を見せて、それが次の作る人を作る教育になる。しかし昨今の状況ではそれがどんどん難しくなってきている気がします。これからの大学や学校には期待している一方で、不安でもあるのですが、杉山先生はいかがですか。
杉山:
まさしくその通りだと思っています。そして、われわれデジタルハリウッド大学みたいなところは、研究者を作るのかというと、作ってないわけですね。たまに放っておいてもなる人もいますけど(笑)教員には研究者と実務家が半分ずつくらいです。
では、われわれは社会に対してどんな役割を持っているのか。デジタル技術やコンピュータの最前線は研究者の人々、とてつもない理論や技術を生み出していますが、その理論や技術を使ったプロダクトを世の中に直接出している、あるいは社会実装しているわけではないケースがほとんどだと思います。デジタルハリウッドでは、そうした理論や技術を学んだうえで、「これを使ったらこんなにすごい表現ができた」「素晴らしいレベルで社会実装できた」というものを世の中に出していくことを目的としている。そしてそれを見たり体験したりした人には「コンピュータってすごい!」と思ってもらえる、そんな知の第二段階や第三段階で役割を持っているような気がするのです。
今の大学の研究はとても複雑で難しいものになっている。人類がこれまで積み上げてきた知にさらなる知を積み上げ続けているわけですから、自然と最前線で研究ができる人というのはごくごく少数に限られてしまいます。そこまで辿り着けるのは、日本トップレベルの大学でもごく一部の人だけでしょう。こうしたピラミッド的な構造が生まれるのは避けられないとしても、どの部分を担ってゆくかという話になる。そして、われわれが担うのは、それらに基づいて「最前線の研究者たちが到達した高みについて、みんなに『ここまで来たんだ』と、さまざまな表現を通して分かってもらう」ことなのだと思います。
「水を運ぶ者」と、学校と世界の100年のギャップを埋めること
読書猿:
僕はサッカーが好きなんですが、「水を運ぶ者」という言葉があります。これは日本代表の監督も務めたイビチャ・オシムさんの言葉です。彼は哲学者みたいな人で、非常に詩的で美しい表現をするんですね。

(イビチャ・オシム氏。2006年から2007年にかけて日本代表監督を務めた。写真は1999年のSKシュトゥルム・グラーツの監督を務めていたころのもの、ウィキメディア・コモンズによる。クレジット:Radiofabrik Community Media Association Salzburg)
読書猿:
これは「サッカーは、シュートをする人だけでは成り立たない」ということです。サッカーではひとつしかないボールをパスして運んだり、ルーズボールを拾ったりする人がいる。そして相手チームの選手をブロックしたり、空いたピッチ上のスペースを埋めて相手の自由を制限する役割もある。こんな風にボールに直接触れない間も走り回って、試合を動かしている人たちがいる。そうした貢献が積み重なって、初めてシュートをする人が点を取れる。そういった人々に光を当てるという意味で、オシムさんは「水を運ぶ者」という言い方をしていたんです。今回の話に置き換えれば、他の人ができないことをして知の最前線を前に進める人がいる一方で、そうした遠くにある知の水源から僕たちのところへ「水」を運ぶたくさんの人がいる。脚光が当たることはあまりないけれど、目立たないそうした人たちがいて、人類が行う知的営為は成り立っている。
かくいう僕も「水を運ぶ者」として本を書いているつもりなんです。数え切れないほどの先行する知の集積があって、やっと一冊の本が出せる。ただそれも、僕がひとつひとつ、知の水源を回って「水」を汲んできたわけじゃない。たくさんの「水を運ぶ者」のおかげで、僕のような者にも本が書けたんです。だから、その知のバトンを次の人に渡したいと思っています。一人の人間がゼロから知識を拾い集めていたら一生かかってしまうところを、集めたり分類したり整理したりする。これもまた「水を運ぶ」仕事です。みんなが知識を役立てるようにしたり、なにか新しいことを思いつけるようにするための手助けを、微力ながらするということです。
最初に書いた本は『アイデア大全』というタイトルなのですが、僕自身はアイデア豊富な人間ではないんですよ。でも新しい考えを必要とした人は今までにたくさんいた。例えば占い師も哲学者もビジネスマンも経営者も、そして名もない人々も、もうとにかくあらゆる人がアイデアが必要になって、いろいろ悩み、考えてきた。そのやり方をを拾い集めて整理し、辞書のようなものを作れば、つまり「水を運ぶ者」として本を書けば、従来のアイデア本や発想法の本よりも、広がりを持ったアイデアの本が作れると思ったんですね。人類がこれまで重ねてきた知的営為の蓄積に、味方になってもらおうと。

(『アイデア大全』。シンプルな発想法だけでなく、科学技術や芸術、文学、哲学、心理療法、宗教、呪術など多くの分野から「新しい考えを生み出す技法」をまとめた著作)
読書猿:
まだ脱線しますが(笑)、「フィロロギー(Philology)」という言葉があります。日本語に訳すと「文献学」「古典文献学」あたりでしょうか。これは「哲学」を意味する「フィロソフィー(Philosophy)」が「知を愛する(Philo-Sophia)」のに対し、「言葉を愛する(Philo-Logos)」という成り立ちの言葉です。これは哲学者キケロの言葉だとされていて、知や学問の根幹に深く関わる言葉だと思うのです。
文献学というのは、基本的にはテキストを様々な努力をして読む、あるいは解釈する学問です。そして、この営みは「自分よりも前に、自分よりも賢い人がいたはずなのだ」という前提に立たないと始まらない。「わけのわからないことが書いてあるから読めないんだ」となったら終わってしまう。「読む価値や意味があるけれど、今の私には読めない」と信じるからこそ、なんとかして読んでやろう、解読しようと努力するわけです。更に言うと「昔の人は科学も進んでないし、愚かなことを信じてたし、今読むに値するものなんて書けっこない」と思ったら、やっぱりダメです。何か価値あるものを書いて残したのだと信じていなければ、古文書の解読やテキストの解釈なんてできないと思うんです。そういう意味でフィロロギー、文献学は本当に「Philo-Logos」なのだと思います。自分よりも前に言葉(ロゴス/Logos)を残した人がいて、それを愛する、そこに賭けることで成立している。
僕は古文書解読という意味での文献学のプロでも何でもない。しかし、キケロが言った意味での「Philo-Logos」なら僕でもできるのではないか。そう思ったのが、本を書くキッカケになりました。今の研究や学問の最前線は非常に高度で複雑になったがゆえに——つまり、あまりにすごすぎるがゆえに——解釈できるところまで山を登れる人も少ない。登るのは大変だし、山の上の方は空気が薄すぎる。でも山を登る以外にもその高さを知る方法、すごさを知る方法、そして知に対する敬意を伝える方法はあるかもしれない。それをつないで広げていけば、この山はもっと豊かになるのではないか。そう考えて、フィロロギストとして本を書いているようなところがあります。
いわゆる「人文知」は人類が築いてきた知を掘り起こしてまとめてフル活用できるやり方なので、これらを使えば自分一人で考えるよりもずっとマシなことができるはず、マシな方法で考えられるはずなんです。「Philo-Logos」に触れることで「俺はオリジナリティはないけど、バックに人類の知がついてるんだぜ!」となれば、既にたくさんの本が出ていて飽和したようなジャンルでも新しい本が書ける。それが可能なのは、大学や学校が知を積み重ねてきたから、そして「水を運んで」くれたからですよ。そういう意味では、大学や学校にはもっと元気になってほしいとつねづね思っています……と、話が戻ってきてしまいました(笑)。
杉山:
いえ、ありがとうございます(笑)大学や学校に対する応援をいただきましたが、改めて考えると、日本の大学は「何を行っているのだろうか?」「社会に対して、どんな役割を、どう持つのか?」という点については、学生から見てもぼんやりしている状態だと思います。
学校というしくみがよくできていたという話も冒頭で出たと思うのですが、おかげさまで——あるいはそのせいで——100年近く基本的なフォーマットが変わっていない。しかしこの100年で世界は変わった。僕たちはそのギャップのようなものを埋めたいと思っています。そこにコンピュータ、テクノロジーがいいところまで来ているから、取り入れていけるところは取り入れていきたい。そして「水を運ぶ者」の話には非常に感銘を受けました。このような概念や考え方を組み込んだうえで、「バーチャルキャンパス」構築の基礎にしていきたいです。
読書猿:
学校という制度は、あまりにうまくできていたと思うんです。そして、それゆえに更新されず停滞してしまった部分はある。では次に行くべき方角が定まっているかというと、そうでもなく、しかし様々な可能性は広がっていると思います。それを探る過程でダメな事例もたくさん出てくると思うのですが、バーチャルでなら多数のバージョンを作れる。試行錯誤がすごくやりやすいはずです。フィジカルな学校は作るのも壊すのも大変ですが(笑)、ダメになるのを厭わずに、多様なことができる。問題に行き当たったとしても、そこから学んで前に進んでいく。そしてそれをコンピュータがフォローしていく、そんな可能性の切り開き方が見たいです。
囲碁の「AlphaGo」は最終的に自分同士で何億局も対戦して強くなったわけですが、似たようなことがバーチャルキャンパスでもできるとすごい。ただ、そこに人間がどう入っていけるのかというのは大きな問題になるのではないかとも思います。僕たち人間が、その高速回転する「縄跳び」にどう入っていけるのか——といったことを考えるなかで、次の可能性は生まれてくるのかもしれませんね。
(了)
【Sponsored】デジタルハリウッド大学
The post 学びの場をゼロから考え直す。デジタルハリウッド大学が挑む「バーチャルキャンパス」を追え!【第4回: 学びとは何か編】 appeared first on Mogura VR.